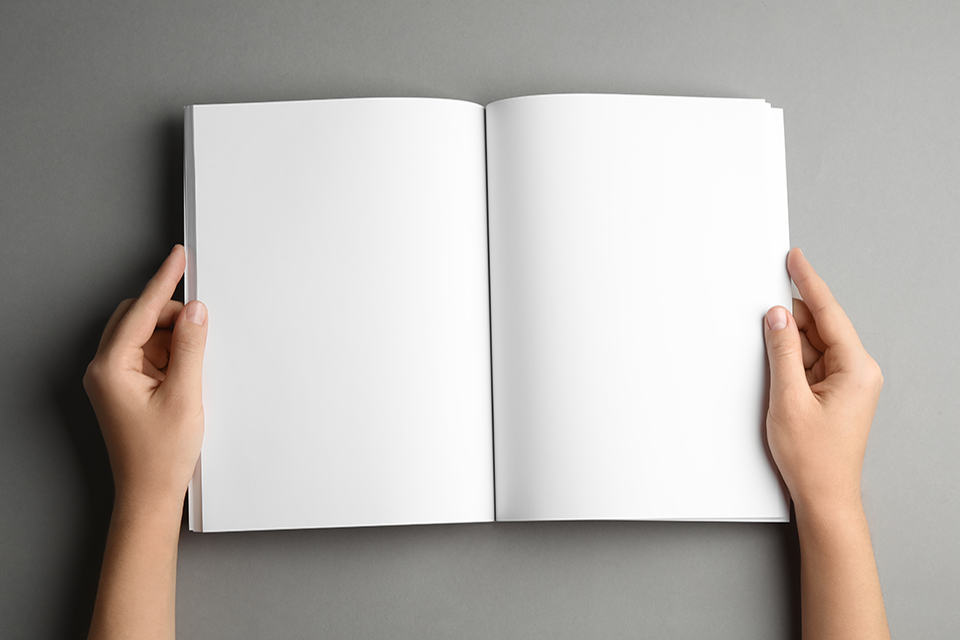「せっかく作ったカタログなのに、手応えがない」──そんな悩み、ありませんか?
製品カタログを作る。
それは単なる「資料作成」ではありません。マーケティング担当者にとっても、デザイナーにとっても、自社の製品を誰よりも愛し、誇りを持って届けるための大切な表現活動です。
…にもかかわらず。
実際の現場では、こんな声を耳にすることが少なくありません。
- 「カタログを渡しても反応が薄い」
- 「営業から“使いづらい”と言われた」
- 「ページ数ばかり増えて、結局伝えたいことが伝わっていない気がする」
じつは、この違和感。
あなただけのものではありません。
製品カタログは、作り手の熱意と、読み手の関心が必ずしも一直線に結びつかない──そんな「ジレンマ」を内包しているメディアなのです。
この記事では、そのジレンマに正面から向き合いながら、
「どうすれば製品の魅力がまっすぐ伝わるカタログが作れるのか?」
を、実務視点で丁寧にひもといていきます。
最後まで読み終えたとき、あなたの中にきっと、
「次のカタログは、こうしてみようかな」という小さな変化が生まれるはずです。
なぜ製品カタログは「伝わらない」のか?
情報過多で埋もれる「主役」
カタログ制作に携わると、必ず直面するのが
「あれもこれも伝えたい」という気持ちとの闘いです。
製品のスペック、開発ストーリー、使い方のバリエーション、コストパフォーマンス…
伝えたい要素は次から次へと湧いてきます。
しかし、情報を盛れば盛るほど、本当に伝えたい核がぼやけてしまうのが現実。
結果として、肝心の「この製品は何がすごいのか?」が伝わらないカタログができあがってしまうのです。
たとえば、こんな経験はないでしょうか?
「製品の良さをきちんと説明したのに、営業現場で“結局何がウリなの?”と聞き返された・・・」
それは、あなたの説明不足ではなく、情報の海に主役が埋もれてしまったせいかもしれません。
「使う場面」を想像していない
もうひとつ、見落としがちなポイントがあります。
それは、「カタログを誰が、どこで、どんなふうに使うのか?」という視点です。
- 営業担当が初回訪問で使う?
- 購買部門が社内稟議用に使う?
- 展示会で立ち寄った人に渡す?
使われるシーンによって、
最適なカタログの情報量・トーン・レイアウト設計はまったく異なります。
にもかかわらず、「とりあえず製品情報を網羅すればいい」と思って作ると、
誰にもフィットしない、宙ぶらりんのカタログになってしまいがちです。
ここに、ちょっとした“あるある”を挟みたいと思います。
【現場あるある】
「展示会向けに作ったカタログが、営業現場では分厚すぎて持ち歩かれない」問題
あなたの作ったカタログ、ちゃんと「現場」で使われていますか?
デザインと訴求ポイントのズレ
さらに、デザイン面でもよくある落とし穴があります。
それは、「見た目の美しさ」にとらわれすぎて、「伝えたいこと」がぼやけてしまうこと。
デザイナーとしては、ビジュアルの統一感や、ブランドトーンの美しさにこだわりたくなるもの。
当然、それは大切なことです。
とはいえ──
読み手にとっては、「オシャレなデザインかどうか」よりも、
「自分にとってメリットがある製品かどうか」が何より重要です。
もし、デザインが製品の魅力を支えるどころか、
逆に「何が言いたいのか分からない」状態を生んでしまったら、本末転倒。
「せっかくカッコよく作ったのに、営業から“これじゃ何も伝わらないよ”と言われた…」
そんな悲しいすれ違いを防ぐために、
デザインは伝えたいことに寄り添うための“手段”であることを、常に意識しておきたいですね。
「伝わるカタログ」を作るための基本設計とは?
製品カタログが「伝わらない」原因は、情報過多や使われ方への無頓着、デザインとのズレにありました。
では逆に、伝わるカタログにするためには、何から考えるべきでしょうか?
ここでは、現場で本当に使える設計のヒントを3つ、紹介していきます。

「誰に届けるか」を1秒で想起させる
カタログを手に取った瞬間、
「これは自分に向けたものだ」と直感できるかどうか。
じつは、これがものすごく重要なポイントです。
たとえば──
- 購買部門向けなら、「コスト削減」「導入事例」を前面に
- 開発部門向けなら、「技術スペック」「カスタマイズ性」を強調
- 営業担当向けなら、「提案しやすいポイント」や「導入メリット」を即伝える
読む相手によって、
何を最初に見せるか、何をどれだけ掘り下げるかが変わります。
ところが、カタログ制作の現場では、
「いろんな部署の人が読むから、全部を網羅したい」
という発想になりがち。
その結果、誰にも強く刺さらない、平均点的なカタログになってしまう…。
まずは、ターゲットを1種類に絞る勇気を持つこと。
どうしても複数ターゲットが必要な場合も、
メインターゲット→サブターゲットという優先順位を明確にしましょう。
ちょっとドキッとする問いかけですが…
「このカタログ、誰に“最初に”手に取ってもらいたいんだっけ?」
この質問に答えられないと、カタログ設計は迷子になってしまいます。
「どの順番で読むか」を設計する
カタログを開いたとき、
自然に視線が流れていき、ストレスなく情報が入ってくるか。
これは、意外なほど重要な設計ポイントです。
人間の目線には一定のパターンがあります。
たとえば、横書き文化の日本では「左上→右下」へと流れる傾向が強い。
この視線の流れを意識して、
- 最初に全体像(製品のUSP)を伝える
- 次に「興味を持った人向け」に詳細を示す
- さらに「導入検討者向け」に事例やFAQを置く
といった読む順番を設計しておくと、
自然な理解→興味→行動の流れを生み出せます。
カタログ全体をひとつの「ストーリー」としてとらえるイメージですね。
とはいえ、現実の制作現場では、
「この情報も入れて」「こっちも目立たせたい」
というリクエストが飛び交いがちです。
結果、どの情報も同じレベルで目立たせてしまい、
読み手が「どこを読めばいいか分からない」カタログになってしまう…。
そんなときは、自分に問いかけてみましょう。
「このカタログ、どこから読むのが一番自然だろう?」
読み手の目線をひとつひとつ追いながら、
設計を見直してみることが大切です。
「感情に触れる」デザイン・コピーを織り込む
製品カタログというと、つい「事実を正確に伝える」ことに意識が向きがちです。
もちろん、それ自体はとても大切な姿勢です。
でも、それだけでは読み手の心は動きません。
なぜなら──
人は感情で動き、理屈で納得するからです。
だから、事実情報だけでなく、
感情を動かすコピーやビジュアル演出を意図的に織り込むべきなのです。
たとえば…
- 【スペックだけで終わらせない】
→「この性能で、あなたの業務がこんなに変わる」まで描く - 【ビジュアルにも物語性を持たせる】
→「現場で使われている風景」をさりげなく挿し込む
これだけで、カタログの印象はがらっと変わります。
そして、ここでも大事な問いかけを。
「このカタログ、読んだ人の心に、どんな感情を残したい?」
ワクワクさせたいのか。安心させたいのか。誇りを持たせたいのか。
──その答えによって、デザインもコピーも変わるはずです。
とはいえ、感情を入れることに抵抗を感じる方もいるかもしれませんね。
「BtoBなのに、そんな情緒的な要素、要るのかな?」と。
でも、じつはBtoBこそ、最後の決め手は人間の心です。
製品スペックを比較するだけなら、一覧表だけでいい。
でも「あなたと一緒に成功したい」と感じてもらうには、心を動かす仕掛けが必要なんです。
実例から学ぶ!伝わるカタログデザインのコツ
ここまで、「伝わらないカタログ」の落とし穴や、
「伝わるための基本設計」についてお伝えしてきました。
でも、頭では分かっていても、
実際にどう形にすればいいのか?というところで悩む方も多いのではないでしょうか。
そこでこの章では、セザックスが実際の制作現場で大切にしている
「伝わるカタログづくりのコツ」をご紹介していきます。
小さな工夫かもしれませんが、
きっとあなたのカタログ制作にもヒントになると嬉しいです!
スペック表ではなく「選びたくなる比較表」へ
カタログにおいて、製品スペックは非常に重要な情報です。
ですが、単に仕様をずらっと並べるだけでは、
読み手にとって「違い」がわかりづらいことも多い。
とくに複数製品を展開している企業においては、
- 「どれを選べばいいか分からない」
- 「スペックの細かい違いがピンとこない」
という読者の戸惑いを招いてしまうリスクも。
そこでセザックスでは、
「選びやすさ」を意識した比較表づくりを心がけています。
たとえば…
- 項目を単なるスペック羅列にせず、**「選択基準」**に沿った並びにする
- 専門用語は必ずわかりやすい言葉に置き換える
- 最後に「こんな方におすすめ」というまとめを添える
こうした工夫を加えるだけで、
読み手の心理的ハードルはぐっと下がります。
じつは比較表って、単なる表ではないんです。
**「導きの手」**なんですね。
あなたのカタログにも、
「どれを選べばいいか分からない」という迷いを、
そっと解きほぐす工夫を忍ばせてみませんか?
一目で魅力が伝わる「ビジュアルストーリー設計」
製品カタログにおいて、ビジュアルは単なる「飾り」ではありません。
ストーリーを語るための、もうひとつの言語だと考えています。
たとえば──
- 製品単体の写真だけでなく、使用シーンを想起させるカットを挿れる
- 順番にめくっていくと、自然に使用イメージが膨らむような流れをつくる
- 背景や色味も、ターゲットの「心象風景」に合わせて調整する
セザックスでは、カタログの最初の段階で
「このカタログをめくった人に、どんな世界観を感じてほしいか?」を徹底的に考えます。
ビジュアルの選定・配置は、単なるセンスや感覚ではありません。
戦略的な設計です。
たとえば、
「新しい働き方を支援するデバイス」のカタログなら、
現代的なオフィス空間で活き活きと働く人々のカットを使う。
それだけで、製品の価値がぐっとリアルに伝わるのです。
【ちょっと想像してみてください】
無機質な白バック製品写真だけのカタログと、
活き活きと使われているシーンを挿れたカタログ。
あなたなら、どちらに惹かれますか?
使われるカタログに欠かせない「持ち運び・閲覧体験」
そして最後に、意外と見落とされがちだけれど
じつはとても重要な視点があります。
それが、
「カタログを持ち歩きたくなるか?」
「読んでいるときにストレスを感じないか?」
という、リアルな閲覧体験です。
たとえば──
- サイズ:A4?B5?持ちやすいか?
- 厚み:カバンに入れやすいか?
- 紙質・重さ:手に取ったときの感触はどうか?
- 開きやすさ:開いたまま置けるか?
こうした物理的な使い心地が、
じつは営業現場や商談シーンでの「使われる・使われない」を左右するのです。
セザックスでは、お客様にカタログ提案をする際、
こうした「リアルな使い勝手」のシミュレーションを必ず行います。
営業担当のカバンに入れて実際に持ち運び、
カフェで広げてみる、移動中にサッと取り出してみる…。
そんな「人間らしい試行錯誤」の積み重ねが、
結果的に、営業現場で愛されるカタログを生み出すのだと実感しています。
「理想」と「現実」のギャップをどう埋めるか
「伝わるカタログ」の設計や工夫について、ここまでさまざまな視点を見てきました。
けれど、実際の制作現場に立つと、“理想どおりには進まない現実”にも向き合わなければなりません。
- 関係者の要望が入り乱れる
- 予算やスケジュールが厳しい
- 社内調整で後戻りが発生する
──こんなこと、ありませんか?
ここでは、そんなリアルなギャップとの向き合い方を、
できるだけ実務に寄り添った形で考えていきましょう。
関係者の意見をまとめる「見える化」とは?
カタログ制作は、マーケティング担当やデザイナーだけで完結する仕事ではありません。
営業部門、開発部門、製造部門、さらには経営層…。
さまざまな部署の要望や意見が入り交じります。
よくあるのは、こんな場面。
「営業はもっと価格アピールを強くしろと言うけれど、開発はスペック重視を譲らない」
「上層部から“もっと高級感を出してほしい”と突然指示が入った」
このままでは、誰もが少しずつ満足し、誰も本当に納得しないカタログが出来上がってしまう危険性があります。
こうした混乱を防ぐために有効なのが、
「見える化」の徹底です。
たとえば…
- 目的・ターゲット・訴求ポイントを「1枚のシート」に整理して共有
- デザインラフを早めに出して「この方向で進めます」と合意をとる
- 修正リクエストも、できる限り「優先順位付き」で整理してもらう
要するに、
「言った・言わない」の泥沼になる前に、合意形成を可視化する。
これは少し手間に感じるかもしれませんが、
プロジェクト後半での手戻りリスクを劇的に減らしてくれます。
セザックスでも、この「見える化シート」を必ず初期段階で作成しています。
(本当に、あとあと自分たちを助けてくれるんです…!)
工数・予算制約とのバランスを取るには?
理想のカタログ像を描くのは簡単です。
ですが、実際には工数や予算の制約という、動かしがたい現実が立ちはだかります。
たとえば──
- もっと写真撮影を入れたいけど、コスト的に難しい
- もう少しデザインに凝りたいけど、納期が迫っている
こういうとき、どう判断すべきでしょうか?
答えはシンプルです。
「目的に直結するかどうか」で取捨選択する。
たとえば、
「現場で営業が使いやすくなること」が最大の目的なら、
写真の追加よりも、比較表の分かりやすさを優先する。
逆に、
「ブランド価値を高めたい」のであれば、
多少のコストをかけてでもビジュアル訴求にこだわる。
限られたリソースを、
「何を守り、何を諦めるか」の判断基準を持って選び取る。
それが、プロジェクトを迷走させないためのコツです。
そして、ちょっと辛口に聞こえるかもしれませんが…
「すべてを完璧に満たすカタログ」は存在しません。
だからこそ、
“どこに魂を込めるか”を決めることが、制作の本質なんですよね。
失敗しないための「設計段階での注意点」
最後に、
理想と現実のギャップを埋めるために、
設計段階で必ず意識しておきたいポイントをまとめます。
- 「誰が読むか」を最初に決める(ターゲット設定)
- 「どんな場面で使われるか」を想定する(使用シーン想定)
- 「何を最優先で伝えるか」を明文化する(訴求ポイント整理)
- 「関係者レビュー」のタイミングを設計段階で決めておく
特に、関係者レビューは後になればなるほど爆発します。
「そろそろ完成です」と思ってから、
「ここ直して」「あれも加えて」と言われると、
誰も幸せになれないですよね…。
だから、
途中経過でもいいから早めに見せる
荒いラフでも方向性を合意する
この意識が、
プロジェクトの安定感をぐっと高めてくれます。
まとめ|「伝わるカタログ」が生む小さな成功体験
製品カタログというものは、
単に情報を並べるだけでは、本当に伝えたい魅力は届きません。
届けたい相手を想像し、
読む流れを設計し、
心に残るストーリーを編み込む。
さらに、
現場で使われるリアルな体験まで丁寧に設計していく。
そんな「人を想う視点」が、伝わるカタログを生み出していきます。
ここまで読んでくださったあなたなら、
きっともう気づいているはずです。
- カタログは、「つくること」がゴールではない。
- カタログは、届けたい想いを、誰かの心に届かせるための手段であることを。
もちろん、現場では、
理想通りに進まないこともあるでしょう。
関係者の意見の板挟みにあったり、
スケジュールや予算に悩んだり。
でも、それでもなお、
ほんの小さな工夫を積み重ねていくことで、
「あのカタログ、すごく分かりやすかった!」
という、現場からのリアルな反応を生み出すことができるのです。
その小さな成功体験が、
やがて営業活動を後押しし、
企業ブランドを育み、
あなた自身の仕事の誇りにもつながっていきます。
──まずはひとつ。
次に取り組むカタログで、今日ご紹介した視点を、どこかにひとつ、取り入れてみてください。
たとえば、
- 「ターゲットを明確に絞る」
- 「視線誘導を意識する」
- 「感情に訴えるビジュアルを加える」
そんな、ほんのひと工夫からでも構いません。
そしてもし、
「もっと深く相談したい」
「プロの目線でサポートしてほしい」
そんな気持ちが芽生えたら──
私たちセザックスが、
あなたのカタログづくりを、心からサポートさせていただきます。
あなたのカタログに、もっと力を。
まずは小さなご相談から、始めてみませんか?